たびノートTOP > 神奈川県
神奈川県
全国の「神奈川県」に関する観光スポット1192件を紹介!
- [絞り込み]
-
- 都道府県
- ジャンル
-
 大黒パーキングエリア
大黒パーキングエリア
- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
- ジャンル
- 見る-観光案内-SA・PA・ハイウェイオアシス
豊富な食事メニューのほか、横浜のおみやげも充実。売店の他に、見て楽しい輸入生活雑貨店が併設している。
-
 保土ヶ谷パーキングエリア(下り)
保土ヶ谷パーキングエリア(下り)
- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
- ジャンル
- 見る-観光案内-SA・PA・ハイウェイオアシス
第三京浜道路下り線、港北インターと保土ヶ谷インターの間にあるパーキングエリア。横浜のおみやげを豊富に揃えている。
-
 都筑パーキングエリア(上り)
都筑パーキングエリア(上り)
- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
- ジャンル
- 見る-観光案内-SA・PA・ハイウェイオアシス
第三京浜道路上り線、港北インターと京浜川崎インターの間にあるパーキングエリア。横浜のおみやげが充実している。
-
 二十五菩薩
二十五菩薩
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群
磨崖仏(俗称二十五菩薩)と呼ばれる史跡。地蔵菩薩24体、阿弥陀如来1体、供養菩薩1体の計26体が巨大な石に彫られている。近くには曽我兄弟の墓や元箱根石仏、石塔群がある。
-
 曽我兄弟の墓
曽我兄弟の墓
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-墓・古墳
富士の裾野で親の仇、工藤祐経を討ち果たした曽我十郎・五郎兄弟の墓。芦之湯史跡探勝歩道の途中にある。鎌倉時代中期〜後期に建てられたといわれ、国の重要文化財に指定されている。
-
 東光庵熊野権現旧跡
東光庵熊野権現旧跡
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-海岸・浜
本居宣長や賀茂真淵といった国学者を中心に、江戸後期の文人墨客の集う場だった東光庵薬師堂。明治時代に取り壊されたが、平成13(2001)年、当時の工法で復元された。
-
 長尾山
長尾山
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-山
標高約1119m。山頂は明るく開けていて眺望抜群の広場のようだ。金時山山頂から長尾山へは上り、下りが繰り返し続く道となっている。
-
 金時手鞠石
金時手鞠石
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群
金時山の登山口から5分ほど山道を登った場所にある巨大な丸い岩。金太郎がこの岩をボールのようにして遊び、蹴落としたといわれている。現在は苔におおわれている。
-
 金時宿り石
金時宿り石
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群
金時山の山中にある巨大な岩。岩は真っ二つに割れており、伝説では、この洞窟で金太郎が母親の山姥と一緒に暮らしていたといわれている。
-
金時山
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-山
金太郎伝説で知られる標高1212mの金時山。山頂から眺める富士山の美しさは名高く、丹沢、南アルプスを展望できる360度のパノラマが楽しめる。
-
 浅間山
浅間山
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-山
古い箱根越えの道の1つである湯坂路にある山で、標高約802m。宮ノ下から登るルートは途中に富士見台というビューポイントがあり、美しい富士山を望むことができる。
-
 湯坂城址
湯坂城址
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-海岸・浜
小田原城の出城として築かれた湯坂城の跡地。室町時代に大森氏によって築かれたといわれる。現在も当時の面影を伝えており、説明版が残っている。
-
 湯坂山
湯坂山
- エリア
- 神奈川県足柄下郡箱根町
- ジャンル
- 見る-自然地形-山
箱根湯本の中心に位置する、標高約546mの山。かつては箱根越えの難所の一つに数えられた。山頂には特に標識はない。
-
 白雲の滝
白雲の滝
- エリア
- 神奈川県足柄下郡湯河原町
- ジャンル
- 遊ぶ-歩く-トレッキングコース・ハイキングコース
落差約30mの絹糸を垂らしたような風情の滝。スギ、マツ、シイなどの原生林に囲まれ、緑と水のコントラストが印象的だ。ハイキングコースの途中、天照山神社の程近くに位置している。
-
 小田原城 天守閣
小田原城 天守閣
- エリア
- 神奈川県小田原市
- ジャンル
- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター
昭和35(1960)年に復興した天守閣の内部は古文書、武具、刀剣などが展示され、標高約60mの最上階からは相模湾が一望できる。
-
 馬の博物館 ポニーセンター
馬の博物館 ポニーセンター
- エリア
- 神奈川県横浜市中区
- ジャンル
- 遊ぶ-キャンプ-キャンプ場・野営場
ポニーやサラブレットなどの馬とふれあえるイベントを開催。天皇賞優勝馬や日本在来馬など、希少な馬たちも見学できる。併設された馬の博物館では、馬文化に関する様々展示を行っている。
-
 岡村天満宮
岡村天満宮
- エリア
- 神奈川県横浜市磯子区
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)
岡村の天神さまとして地元の人に親しまれ、大正時代に活躍しハマっ子に人気のあった大阪役者、市川荒二郎らが寄進した石灯籠も見られる。又撫で牛(石牛)、人気歌手「ゆずの壁画」がある。
-
 英連邦横浜戦死者墓地
英連邦横浜戦死者墓地
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-墓・古墳
太平洋戦争で捕虜となり、日本で亡くなった約1800人が葬られている。横浜市児童遊園地の隣にあり、とても静かで美しい。深い林の中には芝生が植えられ、整然と墓碑が並んでいる。
-
 富岡八幡宮
富岡八幡宮
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)
この地が埋め立てられる前は島のように突き出ていて、応長の津波のときに部落を守ったといわれることから、「波除八幡」の別名がある。毎年7月と9月に祭礼が行われる。
-
 正覚寺
正覚寺
- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)
文禄2(1953)年建立の寺で、天台宗の長窪山総泰院正覚寺と号し、本尊は虚空蔵菩薩である。一年中花が絶えることがない花の寺として知られる。6月にはショウブとアジサイが美しく咲き誇る。
-
 本覺寺
本覺寺
- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)
鎌倉時代に創建された古刹。境内には神奈川区指定の6本の名木・古木がある。幕末の横浜開港の際は米領事館に指定され、日本で初めてペンキが使用されたのはこの寺だと言われている。
-
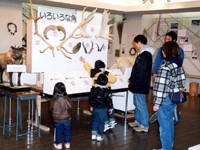 金沢動物園 ののはな館
金沢動物園 ののはな館
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
- ジャンル
- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター
動植物に関する図書コーナーや、金沢自然公園で見られる動植物の展示コーナーや、季節ごとの企画展などがある。また、動物の観察会や工作教室なども開催している。
-
 お林遊歩道
お林遊歩道
- エリア
- 神奈川県足柄下郡真鶴町
- ジャンル
- 遊ぶ-歩く-遊歩道
岬に向かって、森林浴遊歩道と交差するように造られた道。緑が深く、自然観察をするのに適している。道の途中に、野鳥観察舎がある。
-
 ヤクルト本社 湘南化粧品工場(見学)
ヤクルト本社 湘南化粧品工場(見学)
- エリア
- 神奈川県藤沢市
- ジャンル
- 買う-物産販売所-一般みやげもの屋
ヤクルトのオリジナル成分「乳酸菌はっ酵エキス」が入った化粧品を製造している工場。見学ツアーの後は、肌測定や化粧品の体感タイムが楽しめる。
-
 遊行寺
遊行寺
- エリア
- 神奈川県藤沢市
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)
700年の歴史と文化的資料に触れられる場所。敷地内の景観も素晴らしく、四季それぞれに楽しめる。収蔵品は、仏教美術を中心とした多数の絵画、書跡、工芸、時宗の文書で構成されている。
-
 ざる菊園 鈴木三郎さん宅
ざる菊園 鈴木三郎さん宅
- エリア
- 神奈川県小田原市
- ジャンル
- 遊ぶ-歩く-自然探勝路
一株数千の花が作り出すざるを伏せたような球形は見事。色は時期により黄色から白、紫へと変わっていく。赤、エンジなど新種の菊も加わり色鮮やか。苗木の販売もあり。
-
 小田原こどもの森公園わんぱくらんど
小田原こどもの森公園わんぱくらんど
- エリア
- 神奈川県小田原市
- ジャンル
- 買う-物産販売所-一般みやげもの屋
緑に囲まれた広大な敷地が特徴。ポニーや羊などの動物たちとも触れ合え、子供が思う存分遊びまわれる。
-
 報徳二宮神社
報徳二宮神社
- エリア
- 神奈川県小田原市
- ジャンル
- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)
二宮金治郎の名で知られる二宮尊徳翁を御祭神として、誕生地である小田原に創建された神社。隣接する報徳博物館では尊徳翁に関連する多くの文献、遺品、文化財を見学することができる。
-
 開高健記念館
開高健記念館
- エリア
- 神奈川県茅ヶ崎市
- ジャンル
- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター
作家・開高健が晩年暮らした茅ヶ崎の邸宅を記念館として公開。「哲学者の小径」をもつ庭と書斎は往時のまま。
-
 神奈川県総合防災センター
神奈川県総合防災センター
- エリア
- 神奈川県厚木市
- ジャンル
- 見る-文化施設-学習館・科学館
地震・火災・風水害の疑似体験ができる県営の施設。社会科見学の学生も多い。ビデオシアターや消防への通報体験など、あらゆる角度から防災知識を学ぶことができる。家族での来館も歓迎。
掲載情報の一部の著作権は提供元企業等に帰属します。 Copyright(C)2025 Shobunsha Publications,Inc. All rights reserved.
